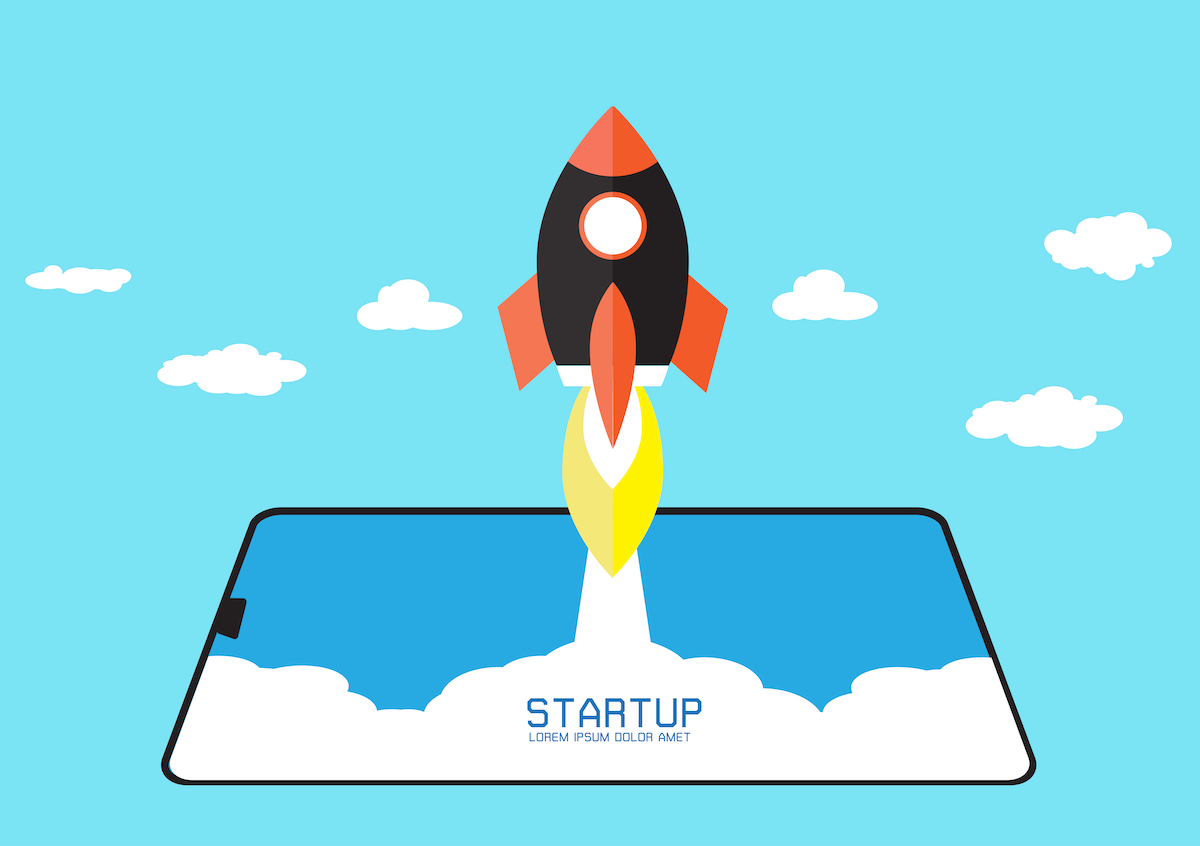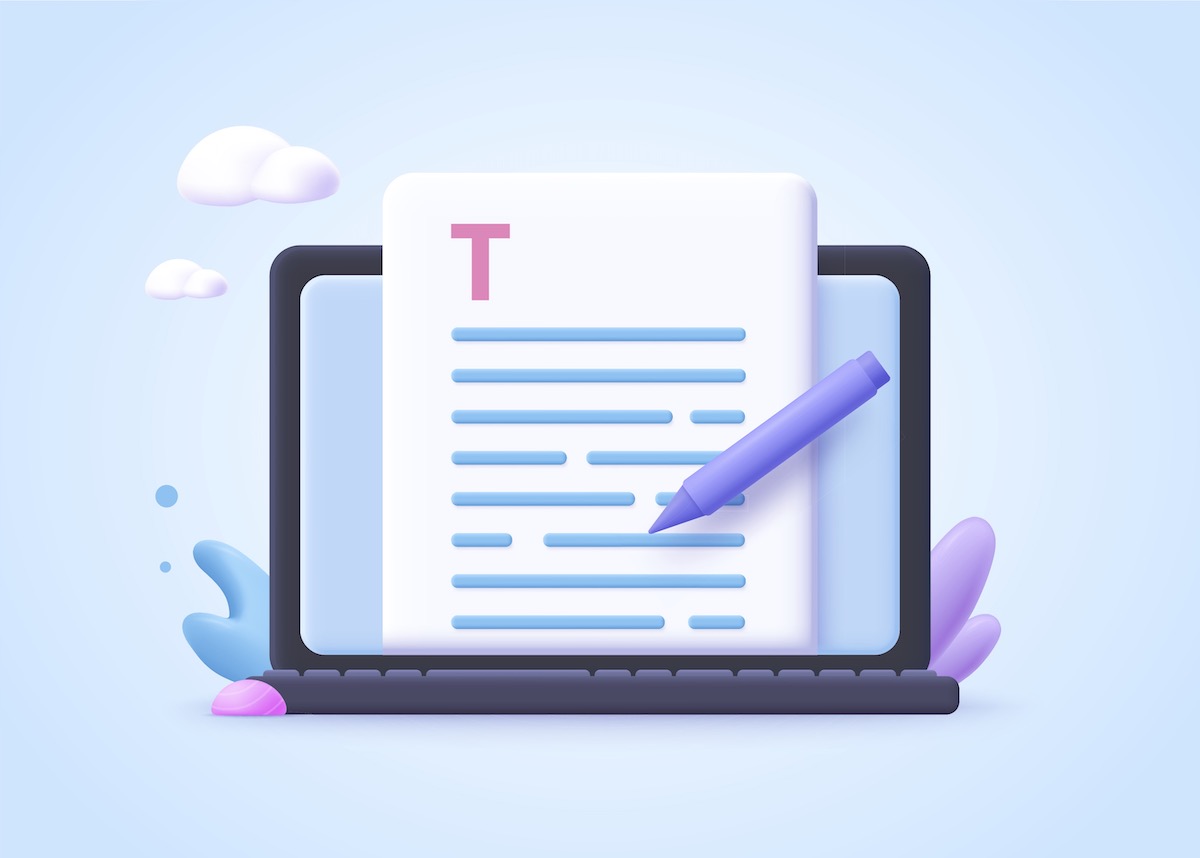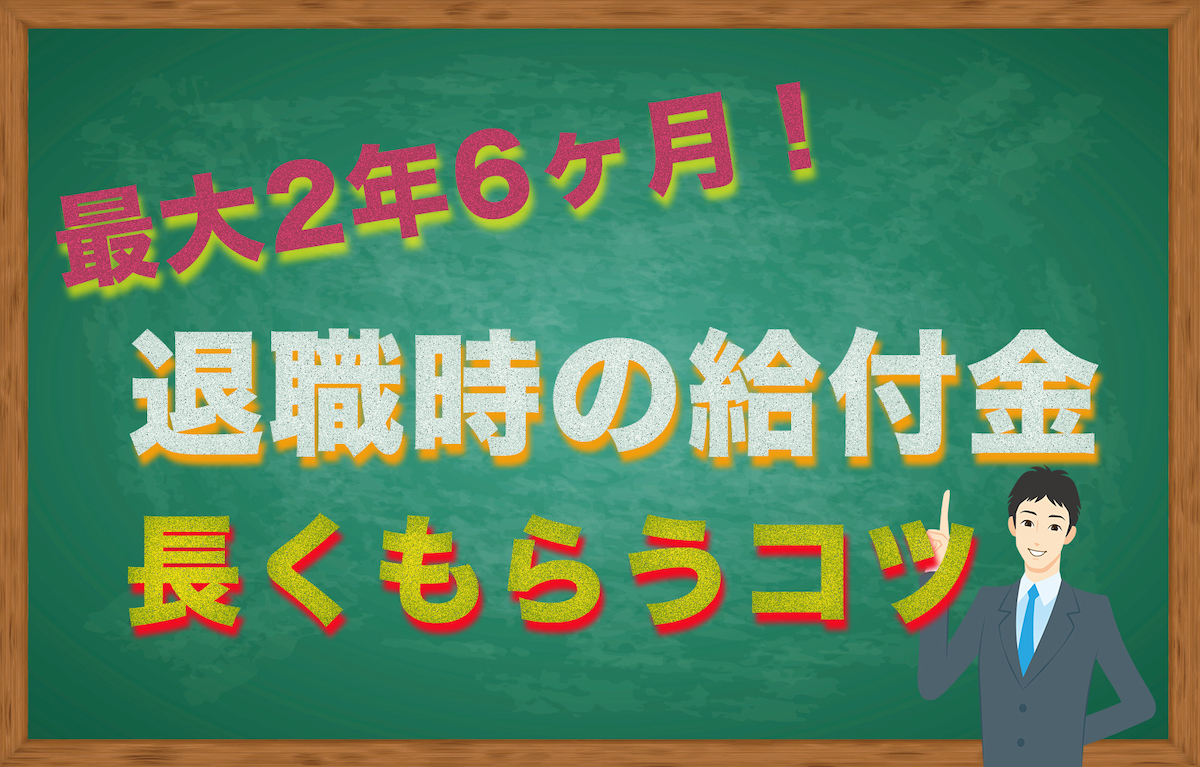やりがいがなくて会社を辞めたいと感じることはよくありますね。
仕事だけでなくプランベートで落ち込んだり意欲がなくなることも多いのではないでしょうか会社をやめると生活も苦しいくなったり転職先がもっと過酷な条件だったらと考えると我慢して働こうと体調まで悪くなってしまうというケースもあります。雇用保険の失業給付をもらいながら転職活動を行う場合、受け取れる期間は退職したときの条件によって違いがありますが自己都合の場合は以外と短いんですよ。これでは体調が治らなかったり、次の職場をゆっくり探す時間もありませんね。少しでも長く失業給付を受け取ったり別の給付金はないのと感じているあなた。社会保険に加入している場合は別の制度の傷病手当金も活用して転職先をしっかり選ぶ環境や体調を整えることも考えましょう。
【こんな疑問に答えます】
- 失業保険(雇用保険の失業給付)はどのくらいの金額?
- 失業保険(雇用保険の失業給付)はどのくらいの期間もらえる?
- 失業保険(雇用保険の失業給付)を伸ばす方法は?
【この記事でわかること】
- 失業保険(雇用保険の失業給付)と傷病手当金の違いと受取手順
- 失業保険(雇用保険の失業給付)の給付金額
- 失業保険(雇用保険の失業給付)の給付期間
- 失業保険(雇用保険の失業給付)と傷病手当金を同時に受け取る方法
失業保険(雇用保険の失業給付)と傷病手当金(社会保険の給付金)は今まで会社に勤めながら払ってきた保険です。
どちらもあなたには活用する権利があります。
しっかり活用して生活を送りながら体調を整え転職先を選ぶことは大切ですね。
雇用保険の失業給付はどのくらいもらえる?傷病手当金と同時にもらう方法も紹介します。
退職するときに少しでも長く給付金を受け取りたい場合は失業保険(雇用保険の失業給付)と傷病手当金(健康保険からでる給付金)の併用も考えましょう。
最長で2年6ヶ月給付金を受け取ることができます。
大きな流れとしては
- 「傷病手当金」で最長1年6ヶ月給付金
- 「失業給付」で最長360日の給付金
となります。
手続きの順番は、
- 会社に在籍しているときに連続して3日以上休む
- 連休期間中に病院へ行く
- 退職日は休む。
- 退職後、健康保険に加入する。(切り替える)
- 傷病手当金の申請準備をする
- 申請用紙を取り寄せ記入する
- 記入した申請書を健康保険に送付(提出)
- 雇用保険の受給期間延長申請を行う。
- 1ヶ月に1回は通院する。
会社で在籍中に事前準備の1〜3番まで行ってしまえば健康保険への手続きとハローワークでの手続きを行うだけで完了しますよ。
失業保険(雇用保険の失業給付)は次の仕事が見つかるまでの就職活動期間に以前まで働いていた会社の給料や期間に応じて受け取ることができる給付金です。申請する場所はハローワークになりますね。
傷病手当金は仕事以外で怪我や病気などで働くことができない場合に健康保険から受け取ることができる給付金です。
受け取るために条件もあるので事前に準備する必要があります。
失業給付金と傷病手当の違いを表でまとめると
| 給付金 | いつもらえるの? | 誰が対象? | 給付金の出どころ |
| 失業給付 | 仕事を辞めて仕事を探している転職活動中 | 会社を辞めた人 | ハローワーク |
| 傷病手当金 | 会社にいるけど病気で休んでいる。 病気や怪我で会社を辞めてしまった。働けなくなった。 |
働けない会社員(元会社員) | 健康保険(社会保険) |
失業保険(雇用保険の失業給付)のポイント
- どんなときにもらえる?
仕事をやめたあと、次の仕事を探しているときにもらえます。
「働く気はあるけど、仕事が見つかっていない人」が対象です。 - 条件は?
ハローワークに登録していること - 仕事をする意思と能力があること
過去に一定期間働いて雇用保険に入っていたこと - もらえるお金の内容は?
前の仕事の給料の一部(だいたい5〜8割くらい)が一定期間もらえます。
傷病手当金(健康保険からでる給付金)のポイント
- どんなときにもらえる?
病気やケガで働けなくなったとき、給料が出ない場合に、健康保険からお金が支払われます。会社に「在籍しているけど休んでいる状態」が対象です。 - 条件は?
会社の健康保険に入っていること(国保では対象外) - 病気やケガで働けない状態が続いていること
給料が出ていないか減っていること - もらえるお金の内容は?
1日あたりの給料の約3分の2が最長で1年6か月もらえます。
退職後でも事前に準備を行っていれば条件が当てはまれば利用することはできますよ。
転職✕退職サポート窓口はこちら
失業保険(雇用保険の失業給付金)の受取金額を紹介します。
雇用保険の失業給付金は退職前6ヶ月の平均給料で基本手当が決まります。
年齢など人によって基本手当に違いがあるんですよ。
給付金計算のポイントは
- 退職前6ヶ月の平均給料で基本手当が決まる。
- 金額目安は退職前の50%〜80%
- 受け取れる基本手当には上限制限がある。
給料は基本給や手当など交通費も含む金額です。
失業保険(雇用保険の失業給付)は次の仕事が見つかるまでの転職活動期間にいままで働いていた給料や期間に応じて受け取ることができる給付金です。申請する場所はハローワークになりますね。
実際にどのくらいの金額が受け取れるのかというと
- 過去6ヶ月の給料を日割りした賃金日割
- 年齢による支給率
で決まります。
受け取れる1日辺りの金額には上限制限があるため高い給料の場合は上限制限で定められてしまう場合もあります。
失業給付金(正確には「基本手当」)がもらえる期間は
- 離職時の年齢
- 雇用保険の加入期間(=就業期間)
- 退職理由(自己都合・会社都合など)
の条件で決まります。
例えば
給料25万円で5年間勤務していた29歳の場合、
給料は基本給+手当など交通費も含む金額となります。
・退職前6か月の総支給額(例:月25万円 × 6か月 = 150万円)
→ 150万円 ÷ 180日(6か月)= 約8,333円(賃金日額)
→ 年齢に応じた割合(たとえば60%)= 8,333円 × 0.6 = 約5,000円
→ 基本手当日額:約5,000円
→ これ × 支給日数(たとえば90日)= 45万円
を受け取ることができます。
給付金の金額と期間を詳しく紹介していきます。
下の表から賃金日額5,000円の支給率は80%になります。
5,000円✕80%=4,000円が基本支給額になりますよ。
29歳の場合以下の場合で見て見ましょう。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 2,868円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円〜4,159円 |
| 5,200円以上12,790円未満 | 80%〜50% | 4,160円〜6,395円(※) |
| 12,790円以上14,130円未満 | 50% | 6,395円〜7,065円 |
| 14,130円以上(上限額) | 7,065円(上限額) |
※5,200円以上12,790円未満の計算方法は、
基本手当=0.8✕賃金日額ー0.3((賃金日額ー5,200)/7,590)✕賃金日額
となります。
次は月給25万円の場合で計算して見ましょう。
賃金日額は25万✕6ヶ月=150万円、150万➗️180日=8,333円になります。
5,200円以上12,790円未満の計算方法で(※)に当てはめると
基本手当=0.8✕賃金日額ー0.3((賃金日額ー5,200)/7,590)✕賃金日額
0.8✕8,333円ー0.3(8,333円ー5,200円/7,590円)✕8,333円=5634.5円
という結果になります。
支給率で見ると67.6%になりますね。
賃金日額12,790円以上14,130円未満は支給率が50%なので一番最初の方法同様で計算できると思います。
賃金日額が14,130円以上の場合は、上限金額の7,065円になりますね。
基本手当は年齢による上限制限があります。
| 年齢 | 1日あたりの上限金額 |
| 〜29歳 | 7,065円 |
| 30歳〜44歳 | 7,845円 |
| 45歳〜59歳 | 8,635円 |
| 60歳〜64歳 | 7,420円 |
上限金額の月給目安は、逆算を行うと
14,130円✕180日➗️6ヶ月=423,900円となります。
この金額を超えている場合には上限金額になりますよ。
他の年齢はこのようになります。
【30歳から44歳】
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 2,868円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円〜4,159円 |
| 5,200円以上12,790円未満 | 80%〜50% | 4,160円〜6,395円(※) |
| 12,790円以上15,690円未満 | 50% | 6,395円〜7,845円 |
| 15,690円以上(上限額) | 7,845円(上限額) |
【45歳から59歳】
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
| 2,868円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円〜4,159円 |
| 5,200円以上12,790円未満 | 80%〜50% | 4,160円〜6,395円(※) |
| 12,790円以上17,270円未満 | 50% | 6,395円〜8,635円 |
| 17,270円以上(上限額) | 8,635円(上限額) |
失業保険(雇用保険の失業給付金)の受取期間を紹介
失業給付金(正確には「基本手当」)がもらえる期間は通常の場合と就職困難者で大きく違いがあります。
・通常の場合は最大で150日
・就職困難者の場合は45歳未満で300日で45歳以上は360日
となります。
通常の場合は以下の3つの条件によって期間が変わりますよ。
- 離職時の年齢
- 雇用保険の加入期間(=就業期間)
- 退職理由(自己都合・会社都合など)
それぞれのパターンを就業期間別に詳しく説明します(※自己都合退職と会社都合退職の両方を記載)。
自己都合で退職した場合(例:自分から辞めた)
| 年齢 | 雇用保険加入期間 | 給付日数(もらえる日数) |
| 全年齢共通 | 1年〜5年未満 | 90日 |
| 全年齢共通 | 5年〜10年未満 | 90日 |
| 全年齢共通 | 10年〜20年未満 | 120日 |
| 全年齢共通 | 20年以上 | 150日 |
※自己都合の場合、基本的に最大150日まで
会社都合で退職した場合(例:倒産、解雇、契約終了など)
| 年齢 | 雇用保険加入期間 | 給付日数(もらえる日数) |
| 〜29歳 | 1年以上 | 90日 |
| 30歳〜34歳 | 1年〜5年未満 | 120日 |
| 30歳〜34歳 | 5年〜10年未満 | 180日 |
| 35歳〜44歳 | 1年〜5年未満 | 150日 |
| 35歳〜44歳 | 5年〜10年未満 | 180日 |
| 35歳〜44歳 | 10年〜20年未満 | 210日 |
| 35歳〜44歳 | 20年以上 | 240日 |
| 45歳〜59歳 | 1年〜5年未満 | 180日 |
| 45歳〜59歳 | 5年〜10年未満 | 240日 |
| 45歳〜59歳 | 10年〜20年未満 | 270日 |
| 45歳〜59歳 | 20年以上 | 330日 |
| 60歳〜64歳 | 1年〜5年未満 | 150日 |
| 60歳〜64歳 | 5年〜10年未満 | 180日 |
| 60歳〜64歳 | 10年〜20年未満 | 210日 |
| 60歳〜64歳 | 20年以上 | 240日 |
となりますよ。
その他にも
- 契約期間満了で更新されなかった
- 病気や介護、妊娠・出産などでやむを得ず退職
- パワハラなどで離職
の場合には特定理由離職者として給付期限が変更になる場合もあるのでハローワークで相談してみましょう。
就職困難者の条件は
| 区分 | 例 |
| 高齢者 | 60歳以上で再就職が難しい人など |
| 障害者 | 身体・知的・精神の障害がある人(手帳の有無は問わない場合もあり) |
| 母子家庭の母など | 母子家庭や父子家庭のひとり親で育児と就労を両立しにくい人 |
| 長期無業者 | 学校卒業後3年以上正社員の経験がない人など |
| 刑務所等出所者 | 更生保護の対象になっている人など |
| DV・人身取引等被害者 | 特別な保護が必要な状態にある人 |
となります。
傷病手当金の退職後に申請する方法を紹介します。
傷病手当金は病気や怪我で仕事ができない場合に健康保険から受け取ることができる制度です。
傷病手当金は最長で1年6ヶ月受け取ることができます。
1年6ヶ月の期間内であれば一度復帰してあとで病状が悪化した場合でも残り期間は受け取ることができます。
退職後でも条件さえ整っていれば申請することができますよ。
仕事中の怪我は労災になるため使うことができないので注意しましょう。
退職後に傷病手当金を受け取るポイントは
- 社会保険に連続して1年以上加入していること。
- 退職前は連休を取る(有給や欠勤でも可)
- 連休期間もしくは事前に病院で診断書を取る。
- 傷病手当金と失業給付は同時に受け取ることはできない。
このが大きなポイントです。
社会保険に1年以上連続して加入していることが条件で国民健康保険では申請することはできませんよ。
傷病手当金と失業保険を同時に受け取ることはもできないんです。
傷病手当金を受け取ってから失業給付を受け取る必要があるんです。
失業給付の受取延長をする必要もありますね。
傷病手当金を退職後に受け取るためには事前に準備する必要があります。
連休を取ることと病院で診断書をもらうことが必要であることを理解しておきましょう。
傷病手当金を受取病気の治療をしたあとで失業給付を受取転職活動をするというのが流れになります。
傷病手当金の計算方法を紹介します。
傷病手当金の金額は過去12ヶ月の平均月報酬で計算されます。
1日辺りの支給額=過去12ヶ月の平均月報酬➗️30✕2/3
で計算することができますよ。
平均の月報酬で1日辺りの平均報酬を計算。
2/3を掛け合わせて金額が支給額になります。
傷病手当金の支給額計算では賞与は含まれません。
交通費は非課税対象の金額は含まず社会保険料の金額に影響を及ぼす課税対象分は含むことができますよ。
給料明細書などで課税対象になっているかどうかでわかりますね。
一覧でまとめると
| 項目 | 傷病手当金の計算に含まれるか |
| 基本給 | ✅含まれる |
| 住宅・役職手当 | ✅含まれる |
| 賞与(ボーナス) | ❌️含まれない。 |
| 交通費 | ⚠️条件付きで含まれる |
参考)国税庁:通勤手当の非課税限度額について
退職後に傷病手当金を受け取る方法を紹介します。
傷病手当金は仕事以外の怪我や病気などで休んでいる期間に社会保険から支給される制度です。
怪我や病気で働けなくなった場合でも受け取ることはできますよ。
会社で働いているときに社会保険に加入して収めてきている訳なので戸惑う必要もありません。
現在はストレス社会で心身ともに疲弊している場合もおおいため、
制度としても確立しています。安心して利用しましょう。
退職後に傷病手当金を受け取るためには在籍期間に準備を進めておく必要があります。
在籍期間に準備する内容は
- 連続して3日以上休む
- 病院に行く
- 退職日は休む
これは確実に行っておきましょう。
連続して3日以上の休みは有給でも欠勤でも構いませんよ。
土日祝が休みの会社であればこちらで3連休でも構いません。
この期間に病院に行ける様に予約もしておくとよいですね。
ポイントは連続で休む事です。
土日が休みで月曜日か金曜日に有給か欠勤でも問題はありません。
土日休んで月曜日は出勤、火曜日に休みなどの場合は連続にならないので注意しましょう。
病院は
- 心療内科
- メンタルクリニック
- 精神科
で原因はついてはわからない(不詳)にしてもらいましょう。
会社でのストレスと告げてしまうと労災になってしまうので支給が困難になってしまいます。
仕事だけでなくプライベートでもストレスを感じるケースは多いので
- 「原因はよくわからないけど不眠で働くことができない」
- 「会社で働くことが難しい」
などで診断を受けましょう。
実際に病院の先生も相談に乗ってもらえますよ。
診断が降りなかった場合は別の病院にも行ってみましょう。
退職日は必ず休んでください。
退職日に出勤をしてしまうと働けると判断されてしまいます。
土日が休みで退職という場合や有給でも欠勤でも構いません。
退職日は必ず休みましょう。
傷病手当金申請の手続き方法を紹介します。
傷病手当金の申請は加入していた健康保険組合で行うことができます。
傷病手当金を申請する方法と実際の手続きの手順は
- 健康保険に加入する。(切り替える)
- 傷病手当金の申請準備をする
- 申請用紙を取り寄せ記入する
- 記入した申請書を健康保険に送付(提出)
- 雇用保険の受給期間延長申請を行う。
- 1ヶ月に1回は通院する。
退職後に傷病手当金を受け取る場合も健康保険に加入する必要があります。
退職後に加入する健康保険は
- 国民健康保険
- 社会保険の任意継続
どちらでも構いませんよ。
安い方に加入するのが良いのですが調べる必要がありますね。
国民健康保険は区役所で保険料を調べてもらいましょう。
社会保険の任意継続は協会けんぽで調べることができます。
協会けんぽ以外の社会保険に加入していた場合は所属先に問い合わせてみましょう。
【豆知識】
年金の免除申請も同時に行いましょう。
国民年金に切り替える場合は年金の免除申請を行いましょう。
所得が少ない、失業した、災害にあった など20歳以上60歳未満で国民健康年金に加入していて
支払いが難しい場合には支払額の全部や一部を免除申請を行うことができます。マイナポータルから申請することもできます。
参考)日本年金機構:国民年金免除制度
傷病手当金の申請に必要な申請用紙は協会けんぽに加入していた場合ダウンロードで入手することができます。
協会けんぽ以外の場合は直接問い合わせを行うか健保連組合を調べてみましょう
申請用紙には
-
- 会社が記載する場所
- 医師が記入する場所
- 自分で記入する場所
の3個所があります。
医師に記入してもらう箇所は病院に通院した時に記入してもらいましょう。
勤務先の会社に記入してもらう場合は郵送で構いません。
会社記入欄に傷病手当金の申請で必要だと伝えて記載してもらいましょう。
書類が揃ったら加入している健康組合に送付を行えば結果の通知が送られてきますよ。
傷病手当金の申請が終わったら雇用保険の受給期間延長の申請を忘れないでください。
病気や怪我などですぐに就職活動が行えない場合は最大4年まで伸ばすことができます。
申請を行っていないと失業給付は退職後1年を過ぎるともらえなくなってしまうので傷病手当金を受け取っている最中に期限がきれてしまいます。
延長手続きは確実に行いましょう。
申請期間は退職後30日から1年位内に申請となりますよ。
| 項目 | 内容 |
| 延長申請できる期間 | 退職の翌日から30日経過後〜1年以内 |
| 最大で延長可能な期間 | 退職の翌日から4年間まで(給付期間はかわらない) |
| 提出先 | ハローワーク(郵送でも可) |
参考)厚生労働省:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)
傷病手当金の受給が終わって失業給付を申請する場合はハローワークで受給期間延長を解除する必要があります。
解除するためには
- 傷病証明書
- 就労可能証明書
が必要になるのでハローワークで受取に行きましょう。
まとめ
会社を退職するとき転職活動をすぐに行うことができれば良いのですが体調不良などで働けない場合もあります。
国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は
- 傷病手当金
- 失業給付
の2種類の給付金で体調面も整えて転職活動を行いましょう。
最長で2年6が月給付金を受け取ることができます。
手続きの順番は、
- 会社に在籍しているときに連続して3日以上休む
- 連休期間中に病院へ行く
- 退職日は休む。
- 退職後、健康保険に加入する。(切り替える)
- 傷病手当金の申請準備をする
- 申請用紙を取り寄せ記入する
- 記入した申請書を健康保険に送付(提出)
- 雇用保険の受給期間延長申請を行う。
- 1ヶ月に1回は通院する。
の通りとなります。